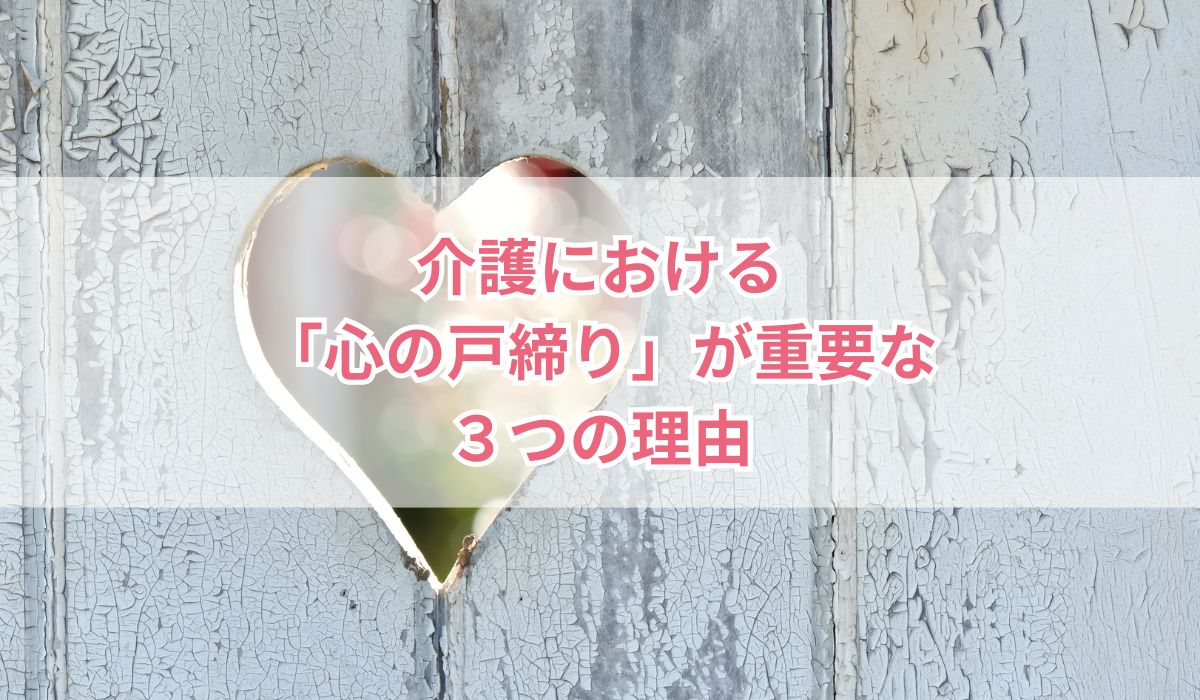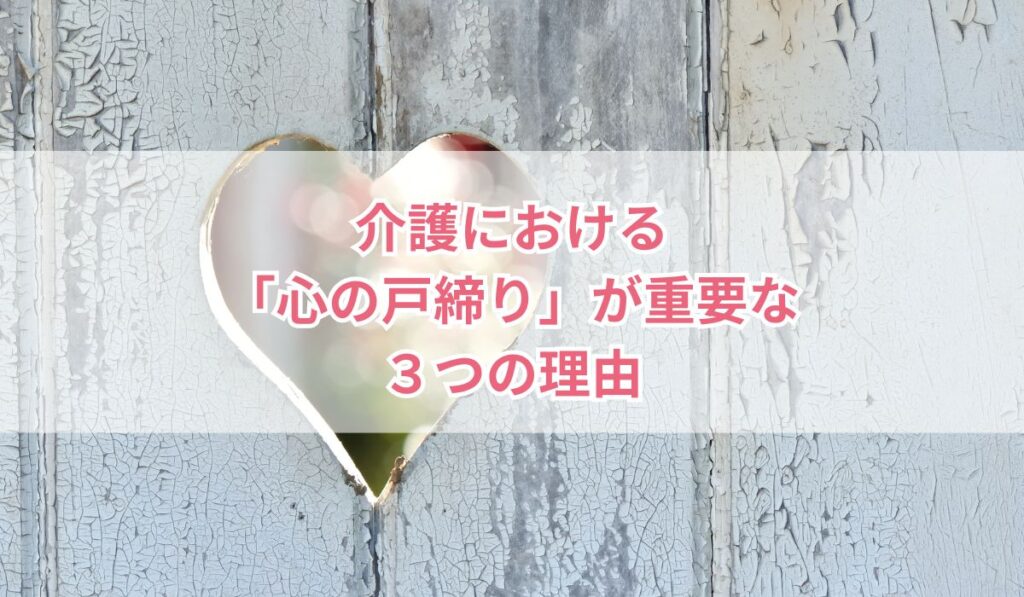
こんにちは!片麻痺の障害がある母の介護歴7年の、はるはるです。
介護をしていると、「もうしんどい」「疲れ切ってしまった」そう感じる瞬間は、きっと何度も訪れたことありますよね。それでも、「やならければならない」という責任感で、すべてを受け入れようとしていませんか。
介護の疲れは、バーンアウト(燃え尽き症候群)、うつ、家庭崩壊などの問題が、引き起こされることも少なくありません。実際私の父は、介護疲れでバーンアウトの症状になりました。
新海誠監督の映画「すずめの戸締り」の主人公に学び、介護における「心の戸締り」の大切さを是非知っておいてください。
「すずめの戸締り」から学ぶ。介護において必要な”心の戸締り”

特に真面目で責任感の強い性格の方は、要注意です。
介護におけるすべてをしようとせず、できないことは「心の戸締り」で割り切ることが、長い介護生活には大変重要なことです。「心の戸締り」がなぜ必要なのか、3つの精神的ケアを確認してください。
心の戸締りが必要な理由|セルフケアのため
映画の中で少女は、突如現れた不気味な”扉”から災いが次々と現れるなか、前を向いて歩み続けていきます。しかしそのためには、時折”心の扉”を閉ざして休息を取る必要がありました。
介護においても同じです。介護の受け手への気遣いやストレスにより、疲労感に押しつぶされそうになることがあります。
介護されている側や、周りの人が何を言っても、「できないものはできない」と、日々の「心の戸締り」を意識しましょう。
一人で全てを背負い込まず、仲間に助けを借りたり、家族に支えてもらうなど、休息を取れる環境を整えることも大切ですね。
心の戸締りが必要な理由| 受け手への適切なケアのため
「すずめの戸締り」の主人公の少女は、思いやりの心を持ち続けたからこそ、前を向いて歩めました。
介護においても、介護されている側の人格を尊重し、その人らしい生活を送れるよう、寄り添う思いやりの気持ちは必要です。
自分自身の心が散漫だと、受け手の気持ちに寄り添えず、適切なケアを提供できませんよね。だからこそ「心の戸締り」で、冷静さと余裕を持って向き合う必要があります。
思いやりの心と合わせて、「心の戸締り」により、質の高いケアを実現できます。
心の戸締りが必要な理由|感情のコントロールのため
介護をする中、わがままや、認知症による振る舞いに、イライラや怒りを覚えることがあると思います。まともに回答したり、相手をすると、必ずトラブルが発生します。
私も介護をする上で、この部分が一番悩みました。ですが、同じ「できない」と言う場合でも、感情的に言葉にするよりも、冷静に言葉にした方が、自分自身の心の状態をプラスに保つことができました。
理不尽な言動にも動じず、冷静に対応できれば、トラブルを未然に防げるかもしれません。
まとめ|介護を続けていくためには「心の戸締り」が重要です
新海誠監督の「すずめの戸締り」に学ぶ「心の戸締り」には、介護において3つの大きな意義があります。
疲れた時こそ、この作品を思い起こし、セルフケア、思いやり、感情コントロールの大切さを意識してみてください。そうすれば、きっと前を向いて歩み続ける勇気とエネルギーが湧いてくるはずです。
一緒に「心の戸締り」で自分の心を第一に守り、介護の在り方を学んでいきましょう!